自動車評論家の塩見智氏がついにマイカーを電気自動車に買い替える決断をしました。マンション住まいで自宅ガレージで基礎充電ができない「充電難民」である塩見氏が選んだのはテスラ「モデル3」のロングレンジです。決断の理由を解説します。
テスラを選んだ理由は「スーパーチャージャーを使えるから」
前回、充電難民(基礎充電環境のない民)にもかかわらずテスラモデル3を購入したことを報告させていただいた(記事はこちら)。国内外の多くのブランドがBEVをラインアップするなかで、テスラを選んだのはなぜか? 正直に言えばBEVのなかでモデル3を最も気に入っていたわけではない。
好き嫌いだけで言えば、買える価格のなかではヒョンデIONIQ 5が一番好きだ。カブトガニみたいなルックスが素敵だ。なのにテスラを選んだのは、一にも二にもCHAdeMO規格の急速充電器ではなくテスラ独自の急速充電インフラである「スーパーチャージャー」を使えるからだ。

基礎充電環境がないということは、「寝ている間に自宅で安い料金で普通充電し、毎朝起きたら満充電」というBEV最大のメリットを享受できない。必然的に充電しにどこかへ出かけ、充電に時間を使わなければならない。もちろんその時間をうまく活用することは可能だろう。しかし言い換えれば、活用しなければならないのだ。どうやっても「寝ている間に……」には勝てない。
であるならば、その時間は短いほうがいい。となると充電出力が重要。モデル3の場合、NMCバッテリーを搭載したモデル(ロングレンジAWDやパフォーマンス)なら最大250kW、LFPバッテリー搭載モデル(RWD)なら同170kWで充電が可能なスーパーチャージャーを使えるテスラのほうが、CHAdeMO充電器を使うそれ以外のブランドのモデルよりも充電に要する時間を短縮できる。
CHAdeMOの充電器や車両も進化しており、最大150kWで充電可能な充電器も車両も徐々に増えてきた。それでも最大150kWだ。しかも最大150kWの高出力急速充電器のネットワークはスーパーチャージャーに比べると心許ない。という考えでまずテスラに絞った。
日本でもNACS規格のEV車種が増えて欲しい
テスラを選んだというよりスーパーチャージャーを選んだという感覚に近い。スーパーチャージャー、すなわちNACS規格をすでに日本でも導入したブランドがあれば、車種選びにはもっと慎重になっただろうし、もっと楽しかっただろう。
ちなみに現時点で日本メーカーとしてNACS規格の日本国内採用を表明しているのはマツダとソニーホンダのみ。
CHAdeMO協議会の意思決定機関である幹事会企業のトヨタ、ホンダ、日産、SUBARU、三菱といったメーカー製モデルの早期NACS国内導入を期待するのは難しいとしても、輸入ブランドが一向に導入しないのは解せない。マツダはある程度自由だから表明できたのかもしれないが、肝心の商品がまだない(2027年登場予定)。
スズキにも期待したい。テスラにとってもスーパーチャージャー使用車種が増えれば利用金額も増え、充電スポット拡充のスピードを上げられるから基本的にウェルカムのはず。JAIA(日本自動車輸入組合)の皆さんの英断に期待したい(ま、トヨタやホンダも組合員なんだけど)。
モデル3とモデルY、RWDとAWDのどちらにするか
次に悩んだのはテスラのどれにするかということ。現在の日本で買えるテスラのEVは、モデル3とモデルYの2車種。それぞれ、価格順に「RWD」、「ロングレンジAWD」、「パフォーマンス(AWD)」というグレードがある。
車種はモデル3でもモデルYでもよかった。どちらも大小のアップデートが繰り返される度に必ずよくなっていることは確認済み。しいて言えば、ちゃんとウインカーレバーが付いている分だけYのほうが好きだ(編集部注※モデル3も直近のアップデートでウインカーレバーが復活しました)。ただ、ここのところ2台連続して大きなSUVを選んだわりに、加齢とともにライフスタイルが変わり、それを活用する使い方をできていなかったので、今回は身軽なセダンでよいかと考えた。都心で停める駐車場の選択肢も増えるし。
大いに悩んだのは、モデル3のロングレンジAWDにするかRWDにするかだ。パフォーマンスは僕にとって過剰な性能なのと高価なので除外した。ロングレンジAWDとRWDの動力性能の違いは大した問題ではない。速いかすごく速いかなので。価格も金利なしローン(前回言い忘れたが、この金利なしキャンペーンも私の背中を押した要因のひとつ)を使えば、月々の支払いはさほど変わらない。
FSD 解禁への期待より先に考えるべきことがあるw LFPで100%かNMCで80%か? 家で充電できないならLFPバッテリー搭載モデルのほうがいいかも。テスラモデル3RWDに乗って考える(YouTube)
ソルトン、テスラモデル3ロングレンジAWDを走らせていたら13年前のフリーモント工場取材のことを思い出した……(YouTube)
バッテリーの基礎知識も抑えておきたい
問題はロングレンジAWDとRWDではバッテリーの総電力量と正極材が異なるということ。ロングレンジAWDが75kWhのNMCバッテリーを搭載し、一充電航続距離706km。対するRWDは54kWhのLFPバッテリーを搭載し、同594km(いずれもWLTCモード)。より実態に近い北米で使われるEPAモードだと一充電航続距離は前者が565km、後者が458kmとなるが、関係性は同じだ。
NMCとLFPでは推奨される充電方法が異なる。大ざっぱに言えば、NMCは頻繁に満充電にすると充電容量が劣化しやすく、可能な限り80%までの充電にとどめる運用が推奨され、LFPは逆に時々満充電にしないと正確な残量(航続可能距離)表示ができないため、積極的に満充電が推奨される。
それぞれの特性が顕著ならわかりやすいのだが、NMCでも時折100%まで充電するのは構わないし、LFPもしょっちゅう満充電にする必要はないという。しかもLFPの場合は一時的に残量表示が正確でなくなっても実際の容量が減るわけではないし、キャリブレーション(残量10%未満から満充電にする)すれば表示の正確さも戻るという。全部曖昧なので判断しづらい。購入前にこの辺りを理解し、判断させる点もBEV導入のハードルの高さのひとつだと思う。慣れ親しんだ燃料よりもすっきりしないこれらの事柄を楽しいと思えるかどうかでBEVを好きか嫌いかが分かれるのかもしれない。
ともあれ、NMCを用いるロングレンジAWDを選んだら80%までの充電を繰り返すことになる。80%充電の場合、一充電航続距離は565km。LFPの場合、日常的に100%まで充電するとして一充電航続距離は594km。一充電航続距離はほぼ変わらないことになる。ただNMCではスーパーチャージャーで最大250kWの充電が可能なのに対し、LFPだと同170kWの最大出力にとどまる。
AWDの直進安定性とオーディオ音質で決断
どちらもテーパーリング(充電して残量が復活すればするほど充電速度が落ちること)するとして、75kWhのNMCを80%まで充電するのと、54kWhのLFPを100%まで充電するのではどっちが充電時間が短くて済む? 基礎充電環境のない充電難民に重要なこの問いをそれぞれのユーザー何人もにぶつけたが、だれに聞いても答えは曖昧だった。
それならとテスラジャパンの広報(メディア対応の担当者)に聞いた。答えは「どっちなんですかね?(ニヤリ)」。ニヤリじゃないのよ(笑)。じゃ、誰に聞きゃいいの? イーロンにXで聞くか!? それぞれ数日間広報車を借り出して充電もしてみても、そんな短い期間じゃ有意なデータは取れない。ほぼ100%曖昧な回答群と、わずかな体験から私が導き出したのは「どっちもどっちで大差ない」という結論だった。
その結果、4WDに起因する直進安定性の高さとオーディオ音質の良さ(スピーカー数が違う)でロングレンジAWDにした。消費行動の決め手というのは案外そのあたりにあるものだ。この記事が掲載されるころには納車されているはずなので、またネタも生まれていると思う。補助金も申請しないといけないし。
【関連記事】
自動車評論家の塩見智氏がマイカーをEVシフト/充電難民がテスラ「モデル3」をポチるまで(2025年9月30日)
文/塩見 智(自動車Ch. ソルトンTV※YouTubeチャンネル)
※記事中写真提供元:Tesla, Inc.




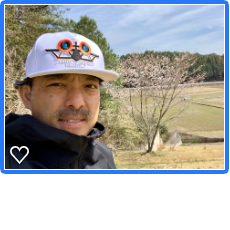









コメント
コメント一覧 (3件)
スパーチャージャーの料金って頻繁に改定されていて最近では充電料金がガソリン車と変わらないか高いくらいって聞きます。充電料金についてのレポートもお願いします。
私も今年三菱アイミーブからテスラモデル3に乗り換えました。一度テスラのスーパーチャジャー(NACS規格)を経験すると、もうチャデモ充電器には戻れないですね!とにかく使い勝手がまるで違います。国内の自動車メーカーはなるべく早くNACS規格を採用しないと、手遅れになると思っています。チャデモ規格を採用している限り、例えEVとしてどんなに優れていても、テスラ車には太刀打ちできないです。
マスクのEVを選ぶ神経が理解できない
一部の脳天気な日本人だけ