2月2日、関東太平洋側でも積雪という予報が出た。ならば、と愛車の日産サクラで雪道テストを敢行した。限られた条件下での走行だがサクラの雪道性能とEVの雪道ドライブの注意点をまとめてみたい。
3度目の正直だった雪道テスト
実はサクラの雪道テストは昨シーズンから考えていた。雪のあるところに行けばテストができると考えて、2024年2月には群馬(水上方面)に遠征したのだが、雪がないタイミングで空振りだった。リベンジを誓い、2025年1月に天気予報をみながら女神湖まで行ったのだが、ここでも空振り。予報どおり前日に雪が降ったものの、きれいに除雪されており道路に雪は残ってなかった。蓼科へ抜ける道に少し残っていた程度で、十分なテストにならなかった。
落胆していたところ、2月2日には寒波が押し寄せ関東地方、都心や平野部でも雪になるという予報が出た。近場で雪が降るなら山のほうにいけばテストができると思い、予定を調整した。予報では箱根、山梨、多摩・秩父では積雪数センチとなっていた。当日、自宅周辺は雨。箱根も雨だったが、富士吉田や山中湖は雪があるという。
予報では、関東の平野部でも雪という予報がでていたので、出発時は、近場なら箱根までいけばなんとかなるだろうと思っていた。しかし、厚木あたりで予報やアプリで現地天気をみても箱根は雨だった。目的地を山中湖方面とした。
山中湖周辺では路面の着雪を確認

雪予報とはいえ、御殿場周辺も雨。なるべく交通量が少ないほうが雪があるとみて、国道246号線の小山の先(菅沼)から県道を使い国道138号に入るルートを選んだ。篭坂峠越えとなるルートだ。国道138号線の入り口でスノータイヤチェックをしていたが、その先、山中湖畔に降りるまでは雪が残っておらずウェット路面だった。
山に入る前、道の駅山北で充電していたので、そのまま湖周辺の別荘地周辺の道路など、県道や市道に入った。除雪は始まっておらず、積雪はおよそ10センチ。轍ができているところはアスファルトが見えているところもあったが、ようやく雪道のドライビングを試すことができた。
ここで、テスト車両についてあらためて仕様・装備をおさらいしておく。
【車両:日産サクラ】
タイヤ:ダンロップ WINTER MAXX(乗用車用スタッドレス)
タイヤサイズ:155/65R14
ホイールサイズ:14×4.5J
夏タイヤは純正アルミホイール(165/55R15)をはいているが、スタッドレスはインチダウン(といっても純正装着サイズ)している。一般的に雪道などは接地面積より接地圧を優先したいので、細めのタイヤを選ぶとよいとされる。また、極端に幅広のタイヤは轍にハンドルをとられやすいことがある。
雪道ではABSをうまく使う
雪質は比較的軽かった。路面に積もったままの雪はさらさらしていた。圧雪状態になっているところもあったが、北海道や豪雪地帯ほどではない。交通量や日当たりの関係でアスファルトの路面が見えているところもあった。
このレベルの雪なら、サクラだから、EVだからという違いは感じられない。ほとんどタイヤの性能といっていいだろう。注意すべき点は一般的なFFでの雪道走行と変わらない。ステアリングは多少軽くなるが、慌てずグリップを確かめながら運転すれば、カーブや対向車とのすれ違いで怖い思いをすることもない。
ただし、雪道、滑りやすい路面では、すべての操作は慎重に行う必要がある。ラフにハンドルを切るとタイヤはグリップせず車はそのまま前に滑る。曲がるつもりでハンドルを切ってもまっすぐ進むので慣れないドライバーはそこでパニックになる。そんなときはブレーキではなく、アクセルを軽く抜いてタイヤがグリップするのを待つのが基本だ。
注意したいのはブレーキ操作だ。雪道でのフットブレーキは姿勢が乱れる元だと思ってほしい。ABSはそれを防いでくれるが、逆にちょっと強めのブレーキでもすぐにABSが作動する。停止したいときはそのままブレーキを強めに踏めばいい。コーナリングでは踏力はそのまま(アクセルはオフ)で曲がるのを待つ。思ったより曲がらないならブレーキを離す(か踏力を弱める)。速度が落ちていればグリップが回復してフロントが曲がり始めるはずだ。
ABS作動中は「ブブブッ」というような断続音や警告音が鳴る。慌てたりパニックになるかもしれないが、この音とクルマの動き(振動)に慣れる必要がある。サクラ(EV)の場合、他の軽より重いのでABSの介入が早いと感じた。
サクラの雪道性能

サクラをはじめとする電気自動車とエンジン車の大きな違いは、雪道では回生ブレーキがとても役に立つ点だ。サクラにはアクセル操作だけで回生ブレーキを活用して加減速をコントロールできる「e-Pedal」機能が搭載されている。私の場合、市街地でも常にe-Pedalをオンにして走っている。このe-Pedalを活用すると、雪道がとても走りやすくなる。
雪が残った下りでも、e-Pedalがオンになっていればアクセルを緩めるだけでスムーズに減速してくれる。回生ブレーキの強度は自動で制御されていて、ほぼ完全停止近くまで減速できる。その挙動は、フットブレーキは言うまでもなく、エンジン車のエンジンブレーキよりもスムーズで安心感が高い。サクラに四輪駆動モデルはないが、e-Pedalを積極的に活用すれば、よほど条件の悪い深雪路でもない限り、一般的なドライバーでも不安なく走ることができるはずだ。
雪質にもよるが、トルクが高いサクラの特性か上り坂でのゼロ発進は駆動輪のスリップロスが多めだった。発進できないほどではないが、フロントが空転している感覚が伝わってくる。インパネにもスリップランプが点いてトラクションコントロールが介入していることがわかる。逆にいえば、細かいことは気にせず発進できるのだが、スリップしている分、上り坂の加速は鈍い。あわてず、ゆっくりアクセルを開きながらスピードが乗るのを待つ。
サクラのモーター制御は、エンジン車より緻密で運転のしやすさを感じるが、スリップやトルク抜けに対する制御がメインだ。姿勢を乱さない、レーンを維持するという基本的な制御が基本となる。
おそらく、もっと雪深くなったり、勾配が急になったりしたら、スタッドレスでもチェーンを巻かないと登らなくなるだろう。念のため金属チェーンを持ってきていたので、そのような状況でも対処できたはずだ。幸い、今回のテストでは坂で登れなくなり立ち往生、引き返すといったことは起きなかった。あえて雪山になど踏み込まなければ、スタッドレスタイヤだけで十分だが、万が一に備えるならチェーンも用意しておくことをおすすめする。
トラクションコントロールの使い方

雪道走行後はタイヤハウスの凍結にも要注意。付着した雪塊は落としておくのがおすすめだ。
なお、トラクションコントロールの介入(スリップ)を避けたいなら、オフにすることもできる。一般的な雪道走行でのオフは勧められないが、スリップが激しい場合、スタック状態から抜け出す場合はオフにするのが有効なケースもある。
トラクションコントロールをオフにした場合、アクセル操作はより精細に行う必要がある。スタックから脱出する場合は、アクセルオンオフを繰り返し車の前後の細かい動きを利用して脱出する方法もある。こうした雪道走行のTIPSは、慣れて覚えるしかない面もある。
雪道走行で肝に銘じておきたいのは、危険なのは登りより下り、発進よりも停止ということだ。EVは、バッテリーの分、同じクラス、グレードに比較すると重くなる。普段使いでは、EVのモーター特性とその制御、低重心によって車の重さを感じることはない。むしろ普段より軽い車を運転している感覚にさえなる。しかし、重量(慣性)は変わってない。EVに限った話ではないが、雪道の下り、カーブ、停止では、その重さ(慣性)の影響はあると思ってほしい。
また、高低差のある狭い雪道ですれ違うクルマがある際は、原則として「上り優先」であることも覚えておくといい。上りの場合、再発進でスタックしやすいリスクがあるからだ。周囲の状況にもよるが、自分が下りならいつでも無理なく停止できるよう速度を抑え、安全な場所で上りのクルマに道を譲ってあげるのがスマートだ。
長距離ならば雪や低温でも電費の悪化は微小
山中湖周辺の雪道を2時間ほど走行すると、除雪車も動き出し交通量が増えてきた。雪もやんでおり国道の雪は完全に溶けている状態になったので、引き上げることにした。山間部積雪10センチとはいえ関東南部で1日降った程度の雪なので、サクラの雪道性能をすべて試せたとは思わないが、メーカーはもっと過酷な条件でのテストを行っている。
では、EVならでは、サクラならではの雪道性能はあったのか。しいて挙げるなら、雪や低温という条件でも思ったほど電費が落ちなかったことだろう。山登りの区間電費では5km/kWhを切ることもあったが、総移動距離で226kmのトータル電費は8.4km/kWhだった。通年の平均電費とほぼ同じレベルだ。ヒーター、エアコンはつけっぱなしではなかったが室温は22度から23度をキープできていた。
自宅を出たときのSOCは93%。経路充電は2回。御殿場手前から富士吉田方面に上がる手前(道の駅山北)で1回。テスト中に山中湖観光案内所で2回目。帰りは道志みちから国道412号線、国道246号線を使った。

帰路では、メーターのSOCと走行可能距離(予測)がギリギリで16km分ほど残して自宅に到着する予定となった。電費が8から9km/kWhとして2%残で帰れるという計算となる。もう1回充電しようかとも思ったが、すでに街中に戻っていたし、家にたどりつけば自宅充電ができるので問題はない。そのまま走行した。自宅に戻ったときのSOCは8%だった。
愛車の素性を知ることができる雪道ドライブ
サクラでは初めてとなる雪道走行だったが、車の基本的な挙動を再確認できてよかったと思っている。ひさしぶりに運転する楽しさを味わえた。
先ほど、登り坂は後輪に荷重がかかるのでFFは苦手と述べた。もちろん普通の道で上り坂が苦手なFFなどもはや存在しないが、昔は山道(ダートだったりする)の登りで、FFはバックで登っていくという技があったくらいだ。雪道では車の限界性能が下がるので、そんな特性も体感できる。車の挙動や動きを掴むのにもよい。
安全に十分注意して無理をしなければ、低い速度で、車はハンドル操作やブレーキ操作によって、これほど繊細に反応するものだと認識することができる。車の特性や限界を知るためにも、雪道走行を経験しておくとよい。車の特性や挙動を掴めば、雪道ドライブは楽しいものである。
取材・文/中尾 真二




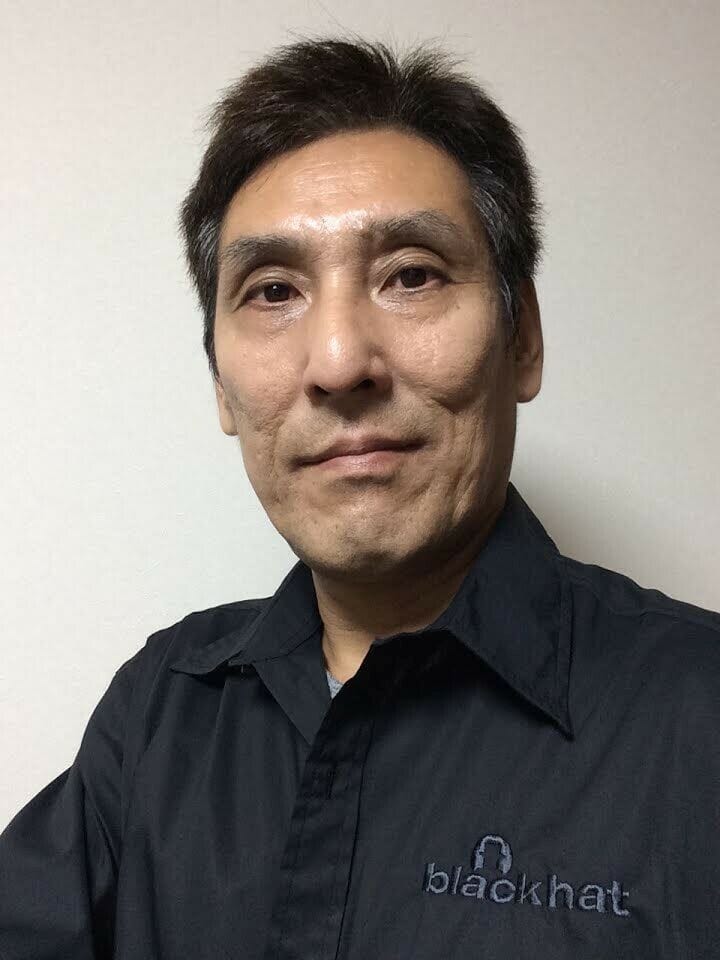









コメント
コメント一覧 (4件)
SAKURA/eKXEV以前にi-MiEVでの雪道経験ありますー。
そもそもi-MiEVはミッドシップ後輪駆動(MR)なんで雪道凍結路不利と言われながら実際はスムーズに止まれましたよ、しかも電動車特有のきめ細やかな制御にも助けられたw
そう考えるとEVの駆動輪は前輪でなく後輪がエエなー思いますー。i-MiEVからeKクロスEVへ乗り換えたら駆動輪スリップの多さに違和感覚えましたし。
何はともあれ路面状況の良し悪しは実体験せねば分からへんから、記事は有効やと思いますー。
ガソリン車の日産デイズFFの重量配分は前62%:後ろ38%で、駆動輪に車重の62%が乗っかります。
同じく前輪駆動の日産サクラの前軸重比率は54%しかなく、このため特に低ミュー路でのトラクション性能はDaysよりも不利となります。
これはサクラ固有ではなく、BEVはFF車よりも前軸重の比率が一般的に小さくなります。
「駆動輪のスリップロスが多め」とお感じになられたのは、このあたりが一つの理由ではないかと考えました。
バックで登るFFって初代シビックかよw
雪道テスト、ご苦労様です。やはりeペダル、使い勝手が良いみたいですね。私はN-VAN e: なので、Bレンジにしても回生が弱く急な下り坂での速度のコントロールはフットブレーキと兼用になります。平坦地での赤信号などでの停止時にはDレンジからBレンジに切り替えてなるべく回生を効かせフットブレーキの使用を最小限にするようにしています。「ガソリン自動車からの乗り換えの違和感を減らす」と謳っていますが、すぐに慣れることですし、「EVの強み=エネルギー回生&物理ブレーキによる摩擦エネルギー損失の低減」を放棄していると感じます。「eペダル」といかないまでも、せめてパドルシフト装着による回生のコントロールくらいは欲しいところです。
文中、「後輪駆動の方がいい」というような主旨の内容がありましたが、雪道では上りに限らず前輪駆動の方が安定し安全です。高速道路でもそうですが、曲がろうとする方向に駆動輪が引っ張るので当然のことです。別の個所で述べているように「ブレーキではなくアクセルを踏んで修正する」ことができるのが前輪駆動の強みです。後輪駆動車は盛大にケツを振ったり轍から抜け出せないことがあるなど雪道ではより不安定で事故の危険が増大します。
それと「雪道での急坂時の離合は上り優先」と記載がありましたが、雪道に限らず近くに待避所等がある場合を除き「常に上り優先」が交通の原則です。坂道をバックすることの危険性が大きいことから「教則」でそのように定められています。