BYDが開催した「バッテリー & SDV」の勉強会から、電気自動車の基礎知識を改めてピックアップして紹介します。後編は、最近よく耳にするけど、よくわからない点が多い「SDV」がテーマです。
【関連記事】
BYDの勉強会から改めて学ぶ電気自動車の基礎知識【前編】リン酸鉄バッテリーの強みと留意点(2025年8月1日)
そもそも、SDVってなに?

メディア向け勉強会では、SDV(Software Defined Vehicle=ソフトウェア・ディファインド・ビークル)に関するBYDの取り組みについて説明がありました。SDVは直訳すると「ソフトウェアが定義する車」です。
わかりやすい例えでは、OSやアプリのアップデートによって機能が高度化するスマホと同じように、ソフトウェアのアップデートで機能、使い勝手が向上していく自動車を意味しています。
従来の車はソフトウェアとハードウェアが一体化していて、どちらか片方だけを手軽にアップデートすることができませんでした。やるとすればチューンナップ的なことになり、当然お金がかかります。
でもSDVになると、ハードウェアはそのままに、ソフトウェアの更新だけで車のライフサイクル全体を通しての機能向上が可能になります。

SDVについて説明するBYDオートジャパン技術顧問の三上龍哉氏。
アップデートは基本的にOTA

ソフトウェアの更新はスマホと同じように、オンラインで実行されるのが基本です。自動車業界で最近よく耳にする「OTA(Over The Air)」です。
例えばテスラではすでに、リコール対応や、自動運転のFSD(Full Self-Driving)の改善などをOTAで実施しています。
ソフトウェアの一部に変更を加えることで長期にわたる機能向上ができれば、車の寿命そのものが伸びる可能性があります。もちろん、それに対応したハードウェアをあらかじめ備えておくことが必要で、その点でもテスラはほかのメーカーに比べて一日の長があるといえます。
IBMは、2030年には自動車関連のイノベーションの90%がソフトウェアによって実現されると予想しています。ハードウェアの改善も同時に進みますが、ソフトウェアのアップデートの速度の方がはるかに早いことがうかがわれます。
SDVでビジネスモデルが大きく変わる
こうしたことから、SDV化の進展は単に車の概念が変わるだけでなく、設計、開発、製造、販売後のサポートまで含めた、車のライフサイクル全体にわたって変革を促すことになると考えられています。
一例を挙げると、PwCコンサルティングは「これまでハードウェア主体の開発や収益モデルで拡大してきた自動車業界にとって、ビジネスモデルの変革が必要」だと指摘しています。
そのひとつが、機能のサブスクリプション化です。スマホやPCのアプリがサブスクによって収益を上げるようになったように、車でもソフトウェア関連ビジネスが拡大するかもしれません。これについてもテスラは、FSDをサブスクにして収益化しています。こうした実績があるため、車のSDV化に先鞭をつけたのはテスラだと言われることがあります。
SDVではFSDに限らず、多様な機能の向上をサブスク化することで、そのひとつひとつを収益化できる可能性があります。ボストンコンサルティンググループと世界経済フォーラムによる2023年の共同調査では、SDVが進化することで2030年までに自動車関連市場の15〜20%に相当する6500億ドル以上の価値が生まれると予想しています。
これでは乗り遅れるわけにいきませんよね。日本でも経産省や国交省がSDV化に向けた取り組みを強化するなど、国を挙げての競争が激化しつつあるのも納得です。
SDVで実現できる技術はこれ
ではSDV関連の技術やサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に理解していきましょう。
●OTA(Over The Air)によるソフトウェアのアップデート
前述したように、ソフトウェアをアップデートすることで車に新しい機能を追加していくことができます。ただ、市場に出ている何万台、何十万台の車の機能更新を販売店などに持ち込んで実施するのは物理的に困難です。
ここで生きるのが、OTAです。基本のソフトウェアをオンラインでアップデートできれば、当面の物理的な問題はクリアできます。初期不良やリコール対応も迅速にでき、ユーザーの不利益を最小化することが可能になります。
OTAはテスラが広範囲な機能改善に利用しているほか、BYDをはじめとする多くのメーカーがインフォテインメントや先進運転支援システム(ADAS=Advanced Driver Assistance Systems)などのアップデートに利用し始めています。
●ADASおよび自動運転機能
カメラやセンサー、ソフトウェアを統合し、機能改善を続けていくADAS関連の技術は、SDVの中でも目に見えるユーザーメリットが大きい機能です。すでに軽自動車から高級車まで、幅広い車種で一般的な機能になっています。またテスラ社のFSDはサブスクで収益化されています。
ADASはEVに限らず、ICE車でもSDV化に向けた重要な要素です。それでも、駆動がデジタル化して、より細かい制御ができるようになったことが、EVへのSDVの恩恵を大きくしています。
●インフォテインメントの進化
ナビゲーションやコネクテッドなどの機能もSDV関連技術の一角を占めます。車がなんらかのクラウドサービスと常につながっていれば、日常的に更新が必要なカーナビをはじめ、車の機能をOTAで頻繁にアップデートできるようになるでしょう。
●予測メンテナンス
AIを使うなどして車両が自前で状態を把握し、問題が発生する前に可能性を予測する機能です。メンテナンスを効率的にできるため、車両の稼働時間を伸ばすことができ、使用者のコスト削減につながります。フォルクスワーゲングループやGMなど一部メーカーで、実装への取り組みが進んでいます。
EVはSDVと親和性の高いパワートレイン
SDVは動力源に関係なく実現可能な概念ですが、内燃機関の車(ICE車)よりも電気自動車(EV)の方がより、効果的に具体化できると考えられます。
ICE車でも電子制御は進んでいますが、EVはその上を行きます。EVは、「走る、曲がる、止まる」の制御のほか、車の価値を判断する大きな要素になるバッテリーの長寿命化やエネルギーマネジメントに関して、ソフトウェアが重要な役割を占めているので、当然といえば当然です。さらに駆動が電気になることで、より詳細な制御をリアルタイムで行うことができるようになります。
EVで特徴的な性能向上のひとつが、一充電あたりの航続距離の延伸や充電性能の向上です。EVは、モーターやインバーター、バッテリー容量などのハードウェアがそのままでも、データを蓄積していくことで制御のポイントを改善することができ、快適性を損なわず航続可能距離を伸ばすことも可能です。
またバッテリー温度、電圧なども含めた充電管理の変更で、充電時の受入電力をアップしたりできます。これらも、テスラ社はすでにOTAで実施してきました。
技術面のキーはECUの統合化
BYDは勉強会で、SDVの取り組みについてOTA(Over The Air)によるソフトウェアのアップデートを強調していました。重点項目のひとつはセキュリティー対策です。
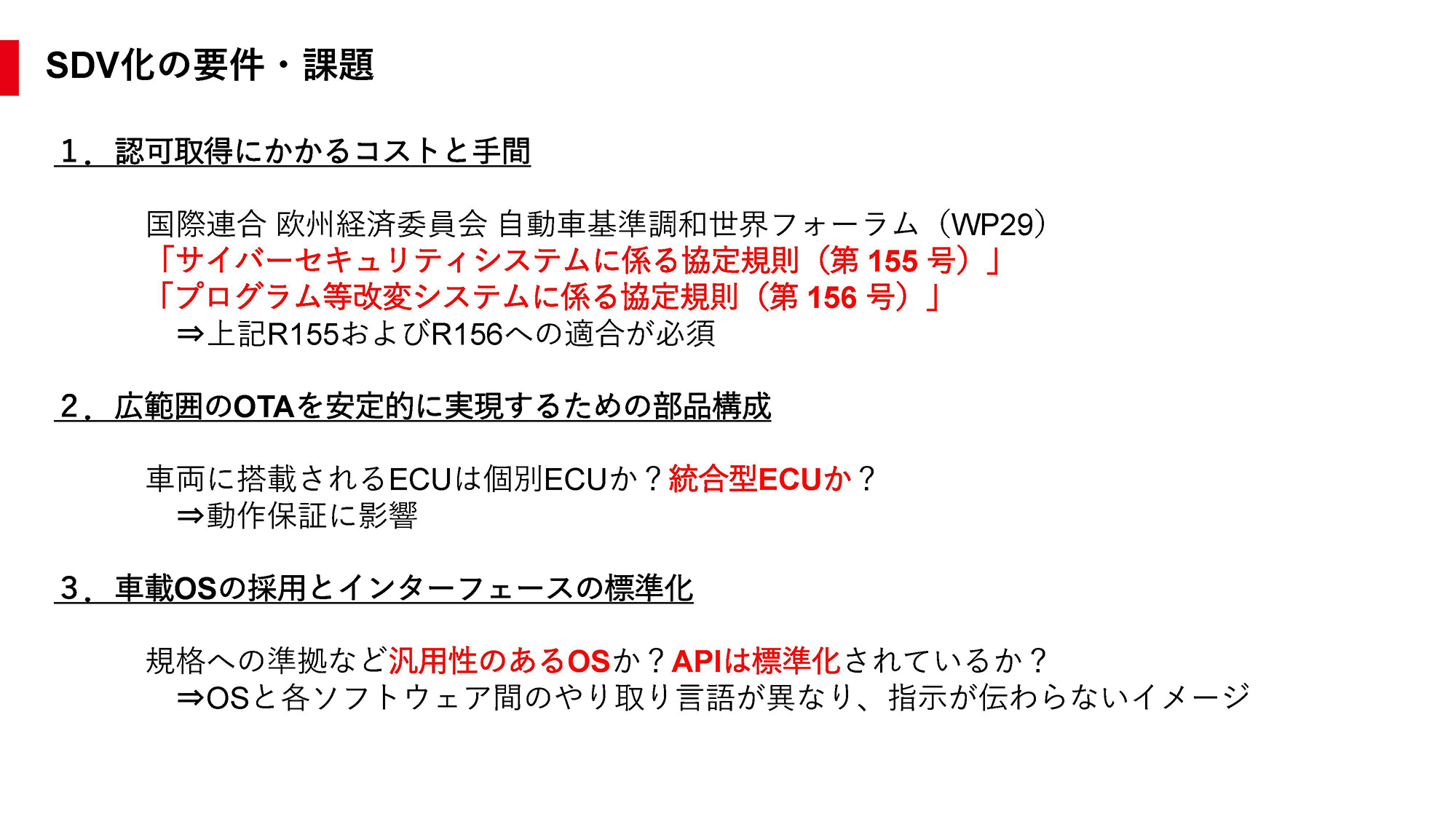
この点について、国連の欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、セキュリティ強化に関する協定が発効していて、適合が必須になっているそうです。
OTAも含めて、SDV化に向けた技術面での重要な動きが、ECUの統合です。従来は、パワートレイン、サスペンション、センサー、アクチュエーター、空調制御などなど、車の機能が増える度にECUが追加される、分散型ECUという構造になっていました。車1台に搭載されているECUの数は100以上になることもあると言われています。
これらのECUを段階的に統合していくことで、①コスト削減と効率化、②開発プロセスの簡素化、③車の機能向上、④OTAによるアップデートの効率向上、などのメリットがあるとされています。
ECUの統合化で最終的に目指すのは、完全な中央集中型です。パソコンのようにひとつのECUで制御できるようになれば、配線や構造の簡略化による重量減、コスト減になります。
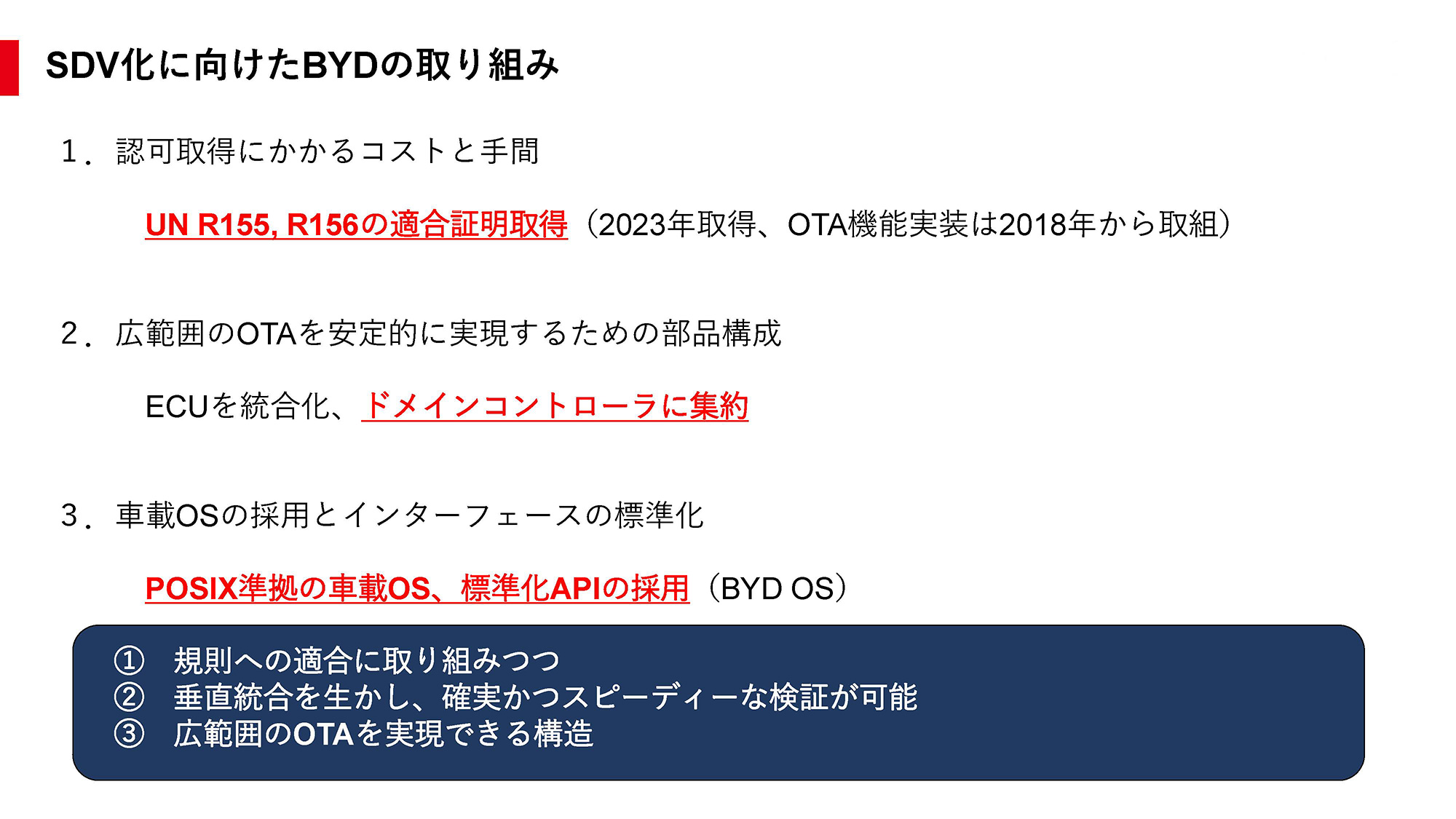
SDVで先を走るテスラ
その前段階として、機能ごとにECUをまとめるドメイン型、車両を前後左右など物理的に区分してECUをまとめるゾーン型の管理技術が採用されつつあります。
この分野でも、最も進んでいるといわれるのはテスラで、ドメインコントローラ化によって数個のECUに統合しているといわれています。
課題もあります。ECUはより高度な性能が求められます。従来のハードウェア中心の設計からソフトウェア中心の設計に移行する必要があるほか、システムの統合も必要で、多額のお金がかかります。サプライチェーンにも大きな影響を及ぼします。
ソフトウェアのコードの行数が現在の1億から2030年までに6億に膨れ上がるという予想もあります。ただこの点については、経産省の資料によればテスラは30万行のC++のコードをAIに置き換えたそうです。全体比では少ないですが、AIの進化速度を考えると急速に状況が変わると考えた方がいいでしょう。
SDVで何を目指すのか
SDV化により、車の機能向上やコスト低減、長寿命化、エコシステムの改善など多くのメリットの創造が期待されています。またもうひとつの重要なメリットは、安全性向上による社会的コストの低減です。
トヨタの豊田章男会長は、SDVの目的は交通事故をゼロにすることだと述べたそうです。先日発表した新型『RAV4』の発表会でそんなエピソードが紹介されたと、複数のメディアが伝えています。
いろいろなメリットや目指すところについて書いてきましたが、SDV化が車をパソコンやスマホのような構造にするのだとすると、SDVという言葉自体はどうでもよくなるかもしれません。何がSDVなのかという話ではなく、いずれは「SDV=自動車」になるのではないでしょうか。
そしてSDV化に向かう中で、電子制御のかたまりのようなEVで何が起きるのか、OTAによるソフトウェアのアップデートはどんな範囲までカバーしていくのか、楽しみは広がります。
ともあれ、楽しくて時には便利で、時にはユーザーや社会にとって継続的なメリットのある車であれば個人的には大歓迎。SDVという言葉にとらわれず、そんな車がどんどん出てくることを期待したいと思います。
取材・文/木野 龍逸













コメント