4ドアポルシェのPHEV、『パナメーラ ターボS Eハイブリッド』に、EVsmartブログチームのジャーナリスト、南陽一浩が試乗。その完成度を試しつつ、普通充電も行ってみた。走行モードの選択によって表情が一変する圧倒的な走りの良さを実感した。
実は電動化の長い伝統をもつポルシェ
ピュアEVスポーツ「タイカン」が市販間近といわれるポルシェだが、それはパナメーラPHEVの立場を危うくすることにはならない。『パナメーラ ターボS Eハイブリッド』は、404kW(550ps)に740Nmもの4リッターV8ターボ・エンジンに、100kW(136ps)&400Nmの電気モーターを組み合わせ、システム全体としてじつに500kW(680ps)&850Nmを誇る。パフォーマンス・カーとして同時代における技術の最高峰を極めることは、じつはポルシェにとっては自然の成り行きなのだ。

じつは電動化に関しても、ポルシェは昨日今日に始めた訳ではない。フェルディナント・ポルシェ博士がローナーポルシェを制作した19世紀末から、インホイールモーターのEVを考案していたのはあまりに有名な話だ。博士は当時の重過ぎるバッテリーに代えて、折衷案として発電用にガソリンエンジンを積んだハイブリッドのパワートレインを考案したほどだ。
いずれ欧州ではCO2排出量を各自動車メーカーが1台あたり平均95g/km以下にしないと2020年よりペナルティが課せられるにも関わらず、足元の充電ステーションの普及がまだまだで密集具合もまばらである以上、100%EVとPHEVの混在がしばらく続くという見通しの方が、ストラテジーとしてもリスクは少ない。ちなみにパナメーラ ターボS EハイブリッドのCO2排出量は66g/km。とはいえドイツ車の常で、十分な航続距離を備えた純電気自動車(BEV)という初出のテクノロジーを載せたモデルは高額で買える層も限られることから、向こう10年はむしろ動力源の一部を電化したモデル、つまりハイブリッドとプラグインハイブリッドが、ポルシェのようなスポーツカーメーカーでも販売の主流になることが予想される。
モデルのバリエーションは?
ポルシェのハイブリッドの元祖、2011年発表の918スパイダーは2013年から918台が市販され、新車価格は約1億円だった。ハイブリッド・テクノロジーがようやくデモクラタイズ(民主化)され、その現行ラインナップで最高峰といえるモデルが「パナメーラ ターボS Eハイブリッド」(税込2831万円)、エントリーモデルが「パナメーラ4 Eハイブリッド」(税込1436万円)という訳だ。

なお、それぞれのモデルには略して「ST」と呼ばれるブレーク版の「スポーツツーリスモ」、「エグゼクティブ」と呼ばれる後席重視のロングホイール版というふたつのボディ・バリエーションもある。

918スパイダーに比べれば確かに「民主化された」とはいえ、それでもパナメーラ ターボS Eハイブリッドの車両価格は税込2831万円。安くはないが、2シーターのスーパースポーツから、大人4人が快適に移動できる居住空間に加え、荷室も備えた日常性の高さと完成度を思えば、確実にその実用面でのレンジは拡がっている。

蛍光イエローのブレーキキャリパーが意味するもの
合計500kW(680ps)&850Nmを受け止める駆動システムは無論4WDで、数値的には荒々しさを想像させるものの、アクセルを踏みこむと、意外なほどジェントルな加速感に驚く。無論、バッテリーが充電された状態では、ゼロ発進では100%電気のみで加速するが、体感上かつメーター読みでは90km/h辺りまで、電気だけで加速していく。走行中に電気モーターからエンジンへとトルクが繋がれる際のマナーも見事で、微かにエンジン始動音がしたと同時に3速または4速ぐらいで、つんのめったりショックを伴ったりすることなく、きわめてシームレスに繋がる。

しかも後で高速道路に入ってから気づいたのだが、100km/h以上の巡航で定速走行の負荷の少ない状態に入った際にも、スキあらば内燃機関がスッと引き上げて電気モーターだけで走ろうとする。つまり、市街地から郊外の高速道路上まで、ハイブリッドオートという走行モードを選択している限り、できるだけ積極的にEVとして走ろうとする、それがパナメーラ ターボS Eハイブリッドのひとつの傾向というか一面だ。

カタログ上、バッテリー容量は14.1kWh、EVモードでの航続距離は22.5km程度(EPA基準 ※WLTCモードでは50km程度)であるものの、巨大なセラミックディスクローターから発生する制動力を回生して、予想していた以上にバッテリー残量の減りは遅い。というか、市街地でストップ&ゴーや下り坂にさしかかる度、回生してバッテリーに貯め込むプロセスが、刻一刻と変化する航続可能距離が、5連メーターの右内側に表示される。効率のよい回生にはある程度の重さが要る、とはドイツ車のエンジニアの弁明のように思っていたが、2.3トンのボディというかマスを動的に制御するこの効率は、やはり大したものだ。

走行モードは他にも、バッテリー残量を減らさないようにする「Eホールド」、エンジンでバッテリー充電を行いながら走る「Eチャージ」が選べ、シリーズ&パラレル両方式を細かく選べるハイブリッドであることが分かる。加えて、これらを数値で読み取らせるだけでなく、グラフィックとして分かりやすくしたるのが、ポルシェの非凡なところでもある。外装のアクセントにもなっている蛍光イエローに注目したい。

このブレーキキャリパーに見られるような蛍光イエローの仕立ては、いかにもPHEV(プラグインハイブリッド)風で、当初は審美的に認めがたかった。だが、さすが機能に与しないディティールをポルシェは用意するはずもない。ナビ画面上で数十km四方のスケールにズームすると、ゼロ・エミッションのレンジ、つまり電気モーターだけで走れる範囲が地図上に蛍光イエローで投影されるのだ。ブレーキキャリパーからナビ画面まで、熱エネルギーがどう始末をつけられるかをイメージしやすくなる、非凡な工夫といえる。


ちなみにセンターコンソールのスイッチ類は、一見するとタッチパネル風に見えて、押し込むとごく短いストロークによる操作感があるという、じつはボタン式。エアコンやシートヒーターといった快適装置だけでなく、走行モード切替やラジオの音量ボリュームまで、触感の上でも明確という、機能的で優れたエルゴノミーはさすが、他の追随を許さない。こういうところもポルシェらしさだ。

さらに走行モード切替だが、先に述べたようなハイブリッド・モード選択のみならず、「スポーツ」や「スポーツプラス」といった、電気モーターも内燃機関も総動員の、パフォーマンス優先のモードも存在する。試しにスポーツモードにして、アクセルを床まで踏んで全開加速を試みると・・・・元より電気モーターの加勢を得た力強い初速とともに、V8ツインターボが野太い爆音を奏で始め、暴力的な加速がいつ果てるともなく続いていく。それでもトルクベクタリングなどのシャシー制御によって、峠でも5m超かつ2.3トンの巨体が、ヒラリヒラリと驚異的に曲がっていく。目眩がするほどの速さだ。なるべくEVモードに入ろうとする傾向の「ハイブリッドオート」時の優等生キャラとははなはだ対照的な、ほとんど二重人格といっていい体育会系キャラに、愕然とするほどだ。

この、エコとハイ・パフォーマンスがジキルとハイドのように同居する二重人格キャラは、330psのV6ツインターボに同じハイブリッド・ユニットが組み合わされ、総合出力340kW(462ps)・700Nmとなるパナメーラ4 Eハイブリッド(車両価格1436万円)にも同じことがいえる。


異なるのは、下から中あたりでのトルクのツキと、上での伸び。つまりエンジンが介入した瞬間の、内燃機関側からのトルクの下支えと、トップエンドに向かって伸びていくパワー感の点で、怪力ぶりという点でV8ツインターボにやはり一歩譲る。が、それでも十分過ぎるほど速くて、公道で持て余すことは確実だが。V6ツインターボのパナメーラ4 Eハイブリッドの方が、V8ツインターボのパナメーラ ターボS Eハイブリッドより200㎏近く車重も軽いはずだが、後者が不可思議なほど重さを感じさせない。それだけベクタリングなどシャシー制御が自然で、回頭性や乗り心地まで洗練されている。


普通充電を試してみた
ところで充電に関しては、日本仕様の車両は入力電圧120-230V/最大電流16Aという規格のチャージャー(ケーブル)を搭載しており、ほぼ空の状態から満充電までの所要時間は充電出力が3kWとして約4時間30分程度という。今回はパナメーラ ターボS Eハイブリッドの方で、バッテリー残量約35%ほどのところから、街場の普通充電(無料)を試してみた。

充電ステーションに繋いで、メーターパネル内における満充電までの必要時間は、5時間40分と表示されていた。気温の関係なのか、やや長過ぎる所要時間ではある。


とはいえ1時間半ほどの所用の後に、バッテリー残量を確かめたところ、航続可能距離換算で31km、75%強のところまで回復(40%以上)。日本国内の一般的な普通充電器でも数時間あれば十分に満充電できるレベルであることは確認できた。

充電ステーションが普及期の欧州では今のところ、「充電がないと動けなくなるEVの方がPHEVより交通弱者」という認識ゆえ、PHEVは急速充電より自宅や勤め先等での普通充電を推奨されているため、現状での現実的な落としどころなのだろう。
(文・写真/ 南陽一浩)

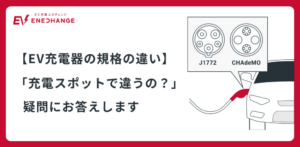












コメント