なぜ、世界はEVを選ぶのか。EVとはどんな自動車で、これからどうあるべきなのか。日本におけるEV普及の先駆者である自動車評論家の舘内端氏が読み解く連載企画。第2回の舞台は1998年のフランスです。
クレルモン・フェランからパリへ
この年、世界で初めてのEVラリーが開催された。1998年9月のことである。パリから南に450km。フランスのほぼ中央の小高い台地にある人口14万人のクレルモン・フェランという、小さいが歴史のある町をスタートして、途中3箇所でスペシャルステージをこなし、パリのコンコルド広場にゴールするという1泊2日のラリーだ。
EVラリーといったが、集合したのはEVだけではない。大会の名称の「ミシュラン・低公害車チャレンジ・ビバンダム」が示すように天然ガス自動車をはじめLPG車、植物燃料車、ガソリン車、ディーゼル車、HEV、ソーラーカー、燃料電池車等、世界から総勢35台のさまざまな低公害車が集まり、「低公害」であることを競うのである。付け加えれば、まだ京都議定書は定まっておらず、自動車の環境問題は排ガスであった。やがてCO2が牙を剥き出す前夜のことだった。

主役はEVだが燃料電池バスも参加
しかし、主役はEVであった。プジョー、シトロエンのフランス勢にフィアットが加わり、さらに日本からは日産の「アルトラEV」と市民団体の日本EVクラブが製作した『EVミゼットⅡ』が参加した。
ちなみにダイムラー・ベンツは燃料電池バスで参加。荷台に何本もの赤い水素ボンベを積んだディーゼルの大型トラックが、水素貯蔵庫としてこのバスに付き従っていた。バスの水素が無くなると、このディーゼルトラックに積まれた水素ボンベから水素を供給する。燃料電地車は大変なのだと改めて感じた。
ダイムラー・ベンツの心意気

クロルモン・フェランを出発しパリに近づくと、大きなバンクのある古いサーキットで、参加車による0-400m加速チャレンジが行われた。ベンツの水素バスのスタートが近づくと、ドアを開けて積み荷のスタッフの旅行用のトランクを放り出した。軽量化である。大きなバスの車重に比べればトランクの重さなど、わずかである。0-400mの加速に果たしてどの程度影響があるのかとも思ったが、競争とはそういう合理主義では理解すべきものではない。ベンツの心意気に感服した。競争はこうでなければならない。
日産アルトラEV
日本から参加した日産のアルトラEV(日本名ルネッサEV)にはリチウムイオン電池が搭載されていた。このラリーのEVの唯一のリチウムイオン電池搭載車だ。日米で販売されており、航続距離は190km以上だった。
しかし、世界初のリチウムイオン電池搭載車はこの1年前にすでに現れていた。現在のEVの激流はこの世界初のリチウムイオン電池搭載車から始まるのである。この話は後ほど。
EVミゼットⅡ
日本勢のもう1台のEVは日本EVクラブが製作したEVミゼットⅡであった。一人乗りの軽トラックのミゼットⅡを改造し、プリウスと同じニッケル水素電池を搭載していた。ラリーでは初日の騒音テストで優勝、2日目の航続距離ランでも優勝した。ちなみに当初のEVミゼットⅡは鉛電池であった。にもかかわらず、交差点GPではBMWのZ4等と対決。0-50mまではZ4をまったく寄せつけず、小生意気なガソリン・スポーツカーに勝利を収めていた。

サーキットイベントでスタートを待つEVミゼットⅡ。
スポーツEVの純血種
プジョーは、当時、Aセグメントで人気だった106をEVにコンバート、2台で参戦してきた。電池は不明だが、速かった。フランスの農村地帯の小道を飛ばしに、飛ばし、あっというまに私たちのEVミゼットを抜き去っていった。

走り去る姿がいい。畑の小道のカーブへの入り方は抜群だった。クルマはこういうふうに走らないといけないというお手本のような走りだった。きっと腕の良いドライバーが乗っているに違いないと思った。予想は当たった。女性ラリーストとしてアウディ・クワトロでWRCで何度も優勝し、ラリー界を席巻したミッシェル・ムートンだった。昼食の席で私たち日本EVクラブのテーブルに来ると、「日本流のマッサージをしてほしい」との要望だ。つまり肩を揉めということだった。恐れ多いのでEVクラブ事務局の女性を差し出した。
プジョー106EVとミッシェル・ムートンの組み合わせは、私の度肝を抜いた。「EVだってぶっ飛んでいいのだ」と教えてくれた。そして、どうせ作るなら、ぶっ飛べるようなEVにしろと。もっとも誰でも彼女のように華麗にドライブできるかは別だが。
ガソリンのプジョー106には、DOHC16バルブ仕様があった。106S16だ。小型、軽量なシャシーにツインカム4バルブエンジンという組み合わせは、ぶっ飛びカーの証明であった。残念ながら試乗の機会に恵まれなかったが。
つまり、プジョー106EVはEVになる前から、狼のたぎる血が流れるスポーツEVの純血種だったということなのだ。それをムートンが操るのだから、それは見事な走りを見せて当たり前である。いいシャシーに、いいモーターとバッテリー、そして腕のいいドライバー。EVだってガンガン走っていいのだ。いや、すべてのEVがそうでなければならない。EVもまた、人を喜ばせる道具なのだから。
EV創生の入り口と京都議定書

1998年のチャレンジ・ビバンダムは、現在に続くEV創世の入り口だった。まず、このラリーが開催される前年の1997年、「京都議定書」が、年の瀬が迫る12月11日、国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で採択された。京都議定書なくしてパリ協定はなく、2050年カーボンフリーもなく、現在のEVシフトの機運は起きなかった。
そして、EVを我慢せずに乗れる自動車にしたリチウムイオン電池の本格的な登場である。日産とソニーが共同で開発したリチウムイオン電池が、フランスでのEVラリーに登場したのだ。まさにリチウムイオン電池が花開く直前の出来事だった。
さらに、HEVのプリウスの登場(1997年)である。「21世紀に間に合った」とのキャッチコピーで登場した世界初の本格的HEVの登場であり、やがて世界の低公害車市場を席巻していくことになった。

初代プリウス。(トヨタ自動車公式サイトより引用)
だが、皮肉なことにHEVからバトンタッチされるリチウムイオン電池のEVがこの時、同じ舞台上ですでに用意されていたのだった。やがて世界の自動車メーカーは自動車の進路を、低公害車であるHEVからゼロ・カーボンカーへと大きく舵を切ることになる。1997年は、HEVの登場と同時にその退場をも暗示した年であった。
1998年には、日本EVクラブ代表の舘内端が、環境大臣表彰を受けた。理由は「低公害車の普及活動」であった。まだ「低公害車」だったのが感慨深い。時代は少しずつだが、確実に変わっていった。
次回はさらに、フランスで体験した示唆深い出来事についてお話ししよう。
(文/舘内 端)

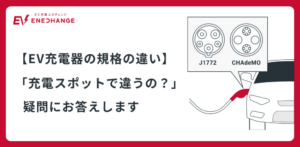












コメント